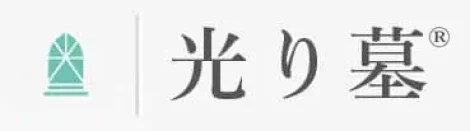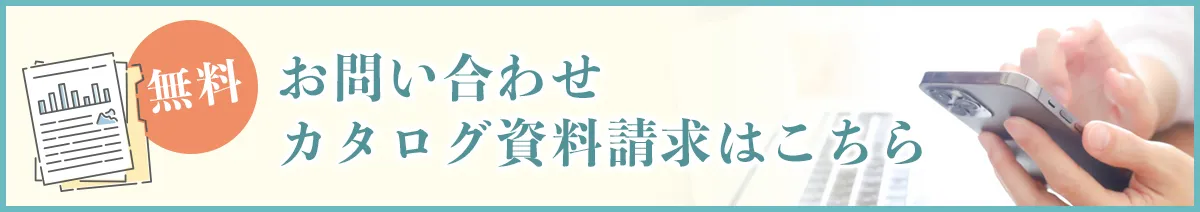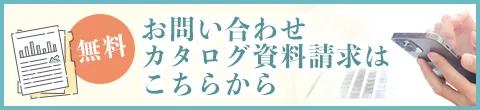現代の日本では、少子高齢化や都市部への人口流入、核家族化などが進むとともに、お墓の管理が難しくなり、お墓を撤去する墓じまいを考える人が増えています。
しかし、実際に墓じまいを行うとなると、さまざまな手間と費用がかかるものです。どれくらいお金を用意すればいいか、支払えるかどうか不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、墓じまいの費用の内訳と相場、安く済ます方法、費用が払えない場合の対処法を紹介します。いざとなって困らないよう、墓じまいにはどういった費用がかかるのかをしっかりと理解しておきましょう。
そもそも墓じまいは必要?無縁墓が増加している背景
近年、お墓の承継者がいない、お墓を継ぎたくない人が多いなどで、放置されてしまう無縁墓が増加しています。
承継する親族や縁故者のいなくなったお墓を無縁墓(むえんぼ、むえんばか)といい、供養する人のいなくなった故人を無縁仏(むえんぼとけ)と呼びます。承継者のいない無縁墓への対応は寺院や墓地によって異なるものの、場合によっては、墓石を撤去されてしまうケースもあるため注意が必要です。
先祖代々のお墓が知らない間に無くなってしまうことがないよう、管理ができなくなった場合は、遺族が墓石の撤去を行う「墓じまい」を検討するようにしましょう。
墓じまい(改葬)にかかる費用総額の平均は約30〜300万円
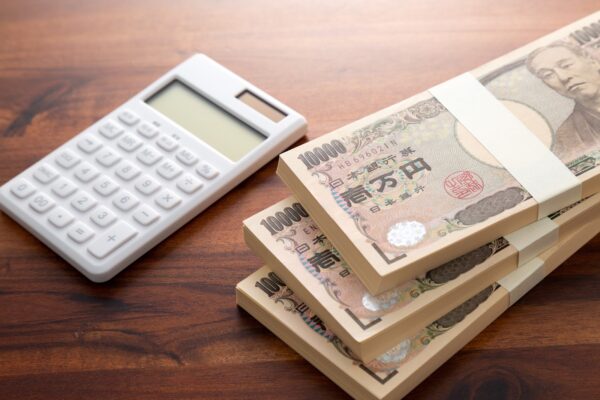
墓じまい(改葬)にかかる費用の相場は、約30~300万円程度です。これには、墓石の撤去費用や、新たな納骨にかかる費用など、様々なものが含まれます。単純に墓石等を撤去する墓じまいだけであるなら20~30万円程度で済みますが、新しいお墓へと遺骨を葬り直す改葬に至っては、撤去費用に加え、多くの費用がかかります。
例えば、その一つに「改葬許可証」が挙げられます。単に”墓石を撤去して終わり”という訳ではなく、改葬ではさまざまな行政機関等への手続きが必要で、その際に各種費用が発生します。また、正しい手続きを取らずに遺骨を放置すると法律違反になってしまうため、遺骨の新たな受け入れ先を証明する「受入証明書」の発行等も行わなくてはなりません。
尚、費用の幅が大きいのは、次の納骨先をどうするかによって金額が変わってくるためです。墓じまい(改葬)の費用は大きく、墓石の撤去、行政手続き、新しい納骨先に関する費用の3種類があります。それぞれをさらに詳しくみていきましょう。
墓石の撤去で発生する費用相場

墓石の撤去に関する費用には、お墓そのものの撤去費用のほか、遺骨を取り出すために法要を行ってもらう費用、檀家を辞めるためにお寺に納める費用の3つがあります。それぞれを詳しく解説します。
墓石撤去費用:約20万円
墓地から墓石の撤去を行って区画を更地にした後、所定の方法で処分してもらうための費用です。墓石の撤去は石材店に依頼するのが一般的で、1㎡あたり10〜15万円程度が費用相場です。
お墓の立地によっては追加費用が必要になる場合もあり、地域によっても費用に差があります。また、遺骨の取り出しも頼む場合は、ほかに3~5万円程度が必要です。
見積もりは自身で近所の石材店に頼むのが普通ですが、民間霊園などでは墓地の管理者から石材店を指定される場合もあります。
僧侶へのお布施代:約5〜10万円
お墓を撤去する際、僧侶を呼んで法要をしてもらうための費用です。遺骨を取り出す際には、お墓から魂を抜いて、ただの石に戻す閉眼供養を行う必要があります。このとき、僧侶を招いて読経をしてもらい、お布施を渡すのが一般的です。
相場はだいたい5~10万円といわれ、基本的には普段の法要と同じくらいの金額で問題ないとされますが、地域やお寺との関係性によっても変わります。僧侶にお墓まで来てもらった場合には、別途お車代として5,000~1万円程度を渡す場合もあります。
菩提寺への離檀料:約3〜20万円
お墓が寺院内にある場合のみ、墓じまいにあたって檀家を辞める(離檀)ための離檀料が必要になります。離檀料は、これまでお世話になったり、お墓を守ってもらったりしたことに対して支払う謝礼のようなものです。
特に法律で決まっているわけではなく、慣習として続いているもので、相場も数万円から10万円以上と幅があります。なかには相場より高い金額をとってトラブルになるケースがある一方、反対に離檀料を不要としてくれるお寺もみられます。
行政手続きで発生する費用相場
墓じまいの際には、自治体や霊園に許可証や証明書などを発行してもらう必要があり、書類交付のため費用がかかります。必要な書類は主に以下の3つです。
・改葬許可証……お墓の撤去に必要となる書類。現在の墓地がある自治体に申請する。
・埋蔵証明書(埋葬証明書、納骨証明書)……現在の霊園管理者から取得する。
・受入証明書……新しい納骨先の管理者に発行してもらう。
手数料はいずれも数百~1,500円程度と大きな金額ではありません。
新しい納骨先で発生する費用相場

お墓の撤去後、遺骨を新しい納骨先に納める際にも、さまざまな費用が発生します。改葬先での費用は、納骨に伴う用意費全般とお寺へのお布施の大きく2つに分かれます。
新しい納骨先の用意費全般:5〜300万円
新しい納骨先で遺骨を納めるのに必要な費用全般です。改葬先は、一般墓所から永代供養墓、樹木葬、手元供養、散骨などさまざまなものがあります。どれを選ぶかで費用に大きな幅があるため、よく話し合って予算に応じた無理のない納骨先を選ぶようにしましょう。
一般墓所や樹木葬は費用が数十万から100万円を超える場合が多く、散骨や手元供養では平均費用を数万円~数十万円に抑えられるケースが多い傾向にあります。
僧侶へのお布施代:約5〜10万円
お墓を撤去する際は閉眼供養を行ってもらいましたが、改葬先に遺骨を納めるときには反対に開眼供養が必要になります。開眼供養は、以前のお墓から抜いた魂を新しい納骨先に入れるための法要です。
閉眼供養と同様、僧侶を呼んで読経してもらう必要があり、その際にお布施を渡すのが一般的です。金額は閉眼供養と同じく5~10万円程度が相場で、お寺によっても異なるため事前に寺院に確認しておくといいでしょう。
お墓を維持できない場合は相続放棄できる?承継するときにかかる費用について

お墓の承継者になると、継続して維持管理費がかかり、墓じまいするにしてもまとまった費用が必要になるため、できれば相続したくないと考える人もいるかもしれません。
しかし、お墓は法律上、先祖や神仏を祀る「祭祀財産」に分類されるため、不動産や現金のような相続対象にならず、放棄もできません。お墓を残すのであれば祭祀継承者が承継し、墓参りや法事などの祭祀を主宰して管理を行う必要があります。
祭祀継承者は原則1人で、選ばれた場合は拒否できません。通常は次の承継者が決まるまでお墓の管理者としての役割が続き、墓じまいを行うかも祭祀継承者が決定権をもちます。
お墓を承継する際の費用としては、相続の対象ではないため相続税はかからないものの、名義変更の手続きを行わなければならず、費用として3,000〜5,000円程度必要です。
墓じまいの費用は誰が払うべき?兄弟姉妹がいる場合は?
墓じまいでは費用が高額になる場合が多く、誰が負担するかは重要な問題です。注意深く検討しないと、トラブルになるケースもあります。
墓じまいの費用は、基本的に今後お墓の権利や管理を引き継ぐ承継者が支払うもので、長男長女が負担するのが一般的です。但し、兄弟姉妹がいる場合は協力しあって均等に負担するケースも多いほか、金銭的に負担が難しい場合には多数の親族が出し合って複数名で分け合うケースもあります。
墓じまいの費用負担者は家庭の事情や状況によって異なるため、誰が払うか事前に家族や親族とよく話し合っておきましょう。最近では終活の一環として、本人が亡くなる前に自分自身でお墓の撤去費用を用意している場合もあります。
墓じまいの費用を安く抑える方法は?

墓じまいには、お墓の撤去だけに限らずさまざまな費用が必要で、新しい納骨先をどこにするかなどで金額が大きく変わります。なるべく金銭的な負担を抑えたい人のために、墓じまいの費用を安く済ませる方法について解説します。
新たな納骨先は費用がかからないものを選ぶ
最初に考えられる手段として、新しい納骨先になるべく費用のかからないところを選ぶ方法があげられます。先述したように、改葬先にはさまざまな選択肢があり、費用も大きく異なります。
あまりこだわりがなく、とにかく費用を抑えたい場合は、散骨や永代供養墓がおすすめです。散骨はお墓が不要で、永代供養墓は他の人と一緒に納骨できる合祀墓であるため、どちらも比較的費用が安く済みます。
それぞれの納骨先についてさらに詳しくみていきましょう。なお、ここで説明するのはあくまで一般的な内容であり、各納骨先でルールや事情が異なる場合がある点には注意して下さい。
他の遺骨と一緒に納める永代供養墓
永代供養とはお墓参りなどが難しくなった遺族のため、寺院や霊園がお墓の管理・供養を行う埋葬方式です。永代供養墓は基本的に集合墓で、不特定多数の他人と一緒に埋葬される合祀です。
はじめに永代供養料を払えば、埋葬後は管理の手間や費用は一切かかりません。お墓を継承する人がいない、事情により将来管理ができなくなる、金銭的な負担を抑えたい人にはおすすめの方法といえます。
但し、一度合祀してしまうと他人の遺骨と混ざってしまい、故人の遺骨を二度と手元に戻せなくなる点には注意が必要です。
樹木や花の近くに納める樹木葬

樹木やお花の近くに遺骨を埋葬して植物を墓標とする埋葬方法で、通常の墓地と違って墓石を建てないのが特徴です。墓石代が必要なく、永代供養で管理費もかからないことが多い傾向にあります。永代供養墓と違い、個別に埋葬してもらえるのもメリットです。
故人に自然に還ってほしいと願う人や費用を抑えたい人、承継者がいないため管理に不安がある人、管理費をかけたくない人などにおすすめです。
それぞれの霊園でユニークな埋葬方法をとっているのも、樹木葬の特徴。例えば、寳光寺「秋川霊園」では、ガラスを使ったお墓「光り墓」による樹木葬を行っています。100万円以内と手頃な価格で追加料金もなく、形や色、デザインなど自分らしいお墓を選ぶことが可能です。

多様化するお墓の1つとして、樹木葬もぜひ候補に入れてみて下さい。
屋内の専用スペースに納める納骨堂
一般的な屋外の墓地と異なり、室内に遺骨を納めるスペースを設けた埋葬方法で、個別で遺骨を安置するロッカー型や礼拝も可能な須弥壇型などがあります。管理費は必要ですが、将来承継者がいなくなってもお墓を撤去する必要がないのがメリットです。
納骨堂はアクセスのよい場所にある場合が多く、天気や土地の状態などを気にせず手軽にお墓参りできるのが魅力です。個別で遺骨を安置したいけれど、外だとお墓の手入れが大変だと感じる人や清潔感のある場所で遺骨を管理してほしい人におすすめです。
遺骨を粉状にして撒く散骨
遺骨を粉状にして山や海など自然に撒く埋葬方法のこと。なかでも海への海洋散骨が主流です。撒いてしまえば終わりのため、その後の管理や維持費などがかからないのが特徴で、近年は認知度も高まっています。
特に法律や規制は設けられていませんが、散骨事業者向けとしてガイドラインを定めている自治体もあります。自分たちで粉状にして撒いても問題ありませんが、基本的なマナーを守る必要はあるため、トラブルなどを避けたい場合は専門業者に依頼するようにして下さい。
遺骨を骨壷やアクセサリーに納める手元供養

手元供養は、遺骨の全部または一部を手元に置いて保管する方法です。小型の骨壺に入れたり、遺骨を収納できるアクセサリーにしまったりと遺骨の保管方法はさまざまで、最近ではおしゃれな骨壺やミニ仏壇、遺骨を身に着けていられるペンダントなど、いろいろな手元供養アイテムが売られています。
管理費なども必要ないため費用を抑えられ、いつも故人を身近に感じていたいという人にも人気です。
墓じまいの業者に依頼する場合は相見積もりをとる
墓じまいを業者に依頼する場合は、必ず複数の業者に見積もりを依頼しましょう。最近では墓じまい業者も増えており、墓石撤去のみの業者や遺骨供養にも対応してもらえる業者など、サービス内容や価格も多種多様です。
1つの業者だけで決めてしまうのではなく、相見積もりをとってサービスと費用のバランスを考えながら、予算とニーズに見合った業者を選ぶことが大切です。
見積もりを出してもらったときは、どの作業にいくらかかるか詳細が明確になっている事を確認し、疑問があれば説明を求めて納得した上で契約するようにして下さい。
墓じまいの費用が払えないときの対処法

墓石の撤去からお寺へのお布施、新しい納骨先への支払いなど、さまざまな費用がかかる墓じまい。なかには金額が数十万円から100万円を超えるケースもあるため、払えなくなるのではと不安に思う人もいるかもしれません。以下では、墓じまいの費用を払うのが難しい場合の対処法を紹介します。
親族に相談して費用を均等に負担してもらう
墓じまいの費用はお墓の管理を引き継ぐ承継者や兄弟姉妹で分担して払うのが一般的とされていますが、それでも負担が大きすぎる場合は親族に費用の支払いを求める方法もあります。
親族の事情にもよりますが、出してもらえる可能性もあるため、困っているのなら抱え込まずに一旦は相談してみるべきでしょう。但し、なかには費用で親族とトラブルになるケースもあるので、十分に話し合いを重ねて納得した上で払ってもらうようにして下さい。
お墓の管理元に相談する
お墓を管理している撤去元の寺院に相談してみるのも1つの方法です。お寺の住職に、墓じまいをしなければならないが負担が大きく支払いが難しいことを伝え、現在の事情を正直に話して下さい。
良心的な寺院であれば相談に乗ってくれ、お布施の金額や離檀料などお寺に支払う費用について考慮してもらえる場合があります。
補助金制度について自治体に相談してみる
自治体によっては、無縁仏を減らすために墓じまいの費用に関する補助金制度を設けている場合があります。無縁仏は自治体が撤去しなければならないため、撤去費用の負担を減らすことが目的です。
例えば、千葉県市川市では、墓地の広さに応じて75,000円~最大440,000円まで原状回復費用を助成する制度を設けています。
すべての自治体に助成があるわけではなく利用できるケースも限られていますが、補助金がなくても何らかの相談に応じてくれる場合があるため、問い合わせてみる価値はあるといえるでしょう。
銀行のメモリアルローンを利用する

最近では、銀行のなかにメモリアルローンと呼ばれるお墓や葬儀に関するローンサービスを提供しているところがあります。
基本的な仕組みは通常のローンと同じで、毎月必要な費用を金利と一緒に少しずつ支払う形になるため、一括で払うより負担を軽減できます。カードローンなどと比べて申し込みが簡単で、収入証明書がいらず、審査も早く終わるのがメリットです。
但し、事前にローンでの支払いが可能かどうか、現在の墓地や新しい納骨先に確認をとるようにしましょう。
まず何から始めるべき?墓じまいの基本的な流れ

お墓の管理が難しくなり、実際に墓じまいを行いたいと思っても、まず何から手をつけていいのかわからない方も多いのではないでしょうか。ここからは、墓じまいを進めるための基本的な流れについて解説します。
家族や親戚、住職に相談する
墓じまいを行う場合、自分1人で進めるのではなく、まずは家族や親戚、住職など関係者に相談して理解を得ることが大切です。
墓じまいすると、二度と現在のお墓にはお参りできなくなります。親族のなかには、お墓を無くしてしまうのに不安や抵抗を覚える人もいるかもしれません。周囲の理解を得ないまま進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあるため、事前によく話し合って同意を得ておきましょう。
寺院墓地の場合は、墓じまいの際、檀家を辞める離檀を巡ってトラブルが起きるケースが考えられるため、あらかじめ住職に話をしておいてください。
新しい納骨先を決める
親族や関係者から理解を得られたら、次は遺骨を移すための新しい納骨先を決めましょう。墓じまいを行った後は、新しいお墓を建てるのか、樹木葬や散骨など別の供養方法を選択するのかを考えておく必要があります。
費用を抑えたい場合は、散骨や永代供養墓など、あまり費用のかからない納骨先を選ぶと良いでしょう。しかし、散骨などの供養方法では、手を合わせてお参りできる場所がなくなってしまうため、親族のなかには抵抗を感じる人がいるかもしれません。
そのため、お参りしやすい場所にお墓を移すなど、費用だけにとらわれず親族全員が納得できる供養方法を検討していくことが大切です。
行政手続きをする
現在の墓地から遺骨を移す際には、役所で所定の手続きを行い、許可をもらう必要があります。あらかじめ改葬先が決まっていると、行政手続きを進めるのもスムーズです。遺骨を移す際には、「改葬許可証」「埋葬証明書」「受入証明書」3種類の書類が必要になります。
現在のお墓がある自治体の役所に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受入証明書」を提出して「改葬許可証」を発行してもらってください。改葬許可証は新しい供養先に遺骨を納める際、管理者に提出する必要があります。改葬許可証の発行に必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
お墓の撤去
役所での手続きを済ませたら、閉眼供養を行い、実際にお墓を撤去・解体していきます。閉眼供養は、墓石に宿った故人の魂を抜き取る儀式で、僧侶にお墓の前で法要を行ってもらうのが一般的です。閉眼供養をしないと、石材店から作業を断られる場合もあるため、きちんと実施するようにしましょう。
供養後は、石材店に依頼して遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地区画を更地に戻し、管理者へ返還します。墓石から遺骨を取り出す作業では、納骨室(カロート)の蓋をしている重い石を動かさなければなりません。一般の方が自分たちで行うのは危険なため、プロの石材店にお願いするようにしてください。
新しい供養先に納骨する
最後に、取り出した遺骨を新しい納骨先に持ち込んで納骨を行い、墓じまいは完了です。新しい供養先に遺骨をもっていく際には、改葬許可証を忘れずに持参しましょう。
納骨前の注意点として、取り出した遺骨に汚れがあったり、骨壺に水が入り込んでいたりしないかを確認しておいてください。問題がある場合は、そのままだとカビが生えてくる恐れがあるため、専門業者に依頼して遺骨の洗浄・乾燥作業を行うと良いでしょう。
また、散骨や手元供養など、供養方法によっては事前に遺骨をパウダー状にしたり、アクセサリーにする場合もあるため、同様に業者への依頼が必要です。
墓じまい後の納骨には光り墓も

少子高齢化や都市化が進む現代日本で、多くの人にとって重要になりつつある墓じまい。お墓の撤去費用だけでなくお寺へのお布施や新しい納骨先へ納める用意費など、墓じまいには多くの費用がかかります。
墓じまいの費用は新しい納骨先や業者を適切に選べば抑えられますが、それでも支払いが難しい場合は、親族や寺院への相談や自治体の補助金や銀行のローンなどを利用してみて下さい。
そして、なにより墓じまいで大切なのは、故人にとって最良の納骨先を見つけることだといえるでしょう。現在では、納骨先にもさまざまな選択肢が生まれています。
美しいアートガラスを使った「光り墓」もその1つ。名前の通りに光を放つように明るい墓石は従来のお墓のイメージを一新してくれます。墓じまいの際には、ぜひ大切な故人の遺骨を納めるのに最適な納骨先を探してみて下さい。